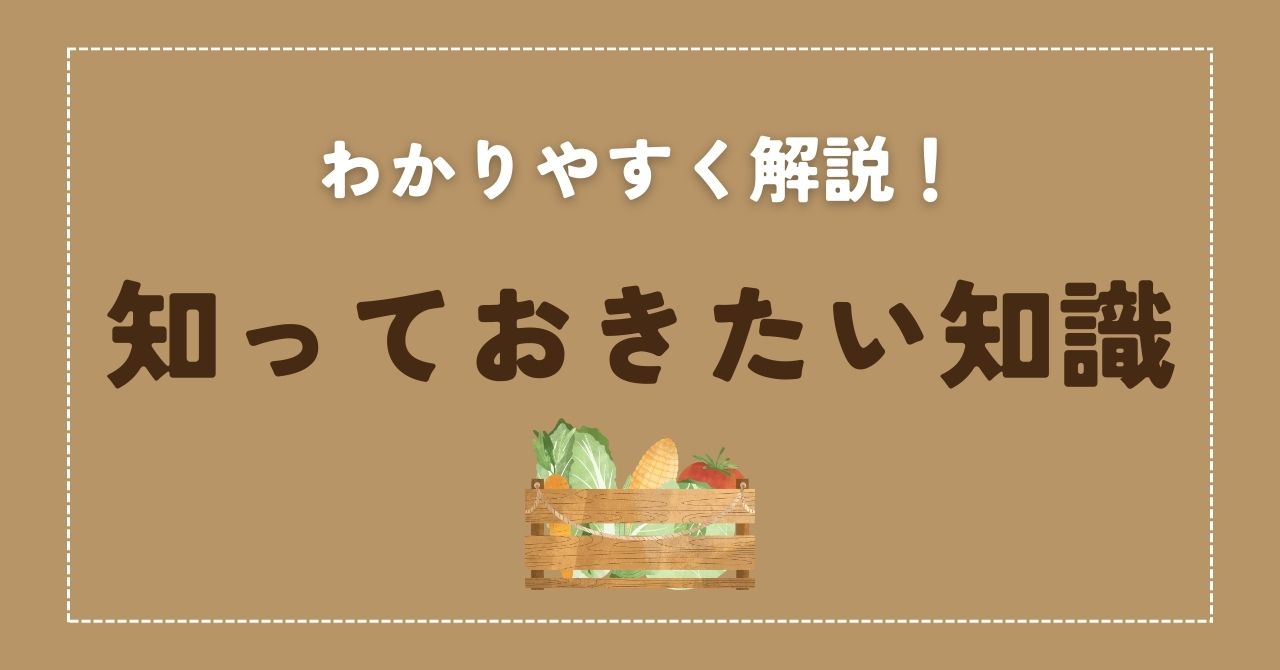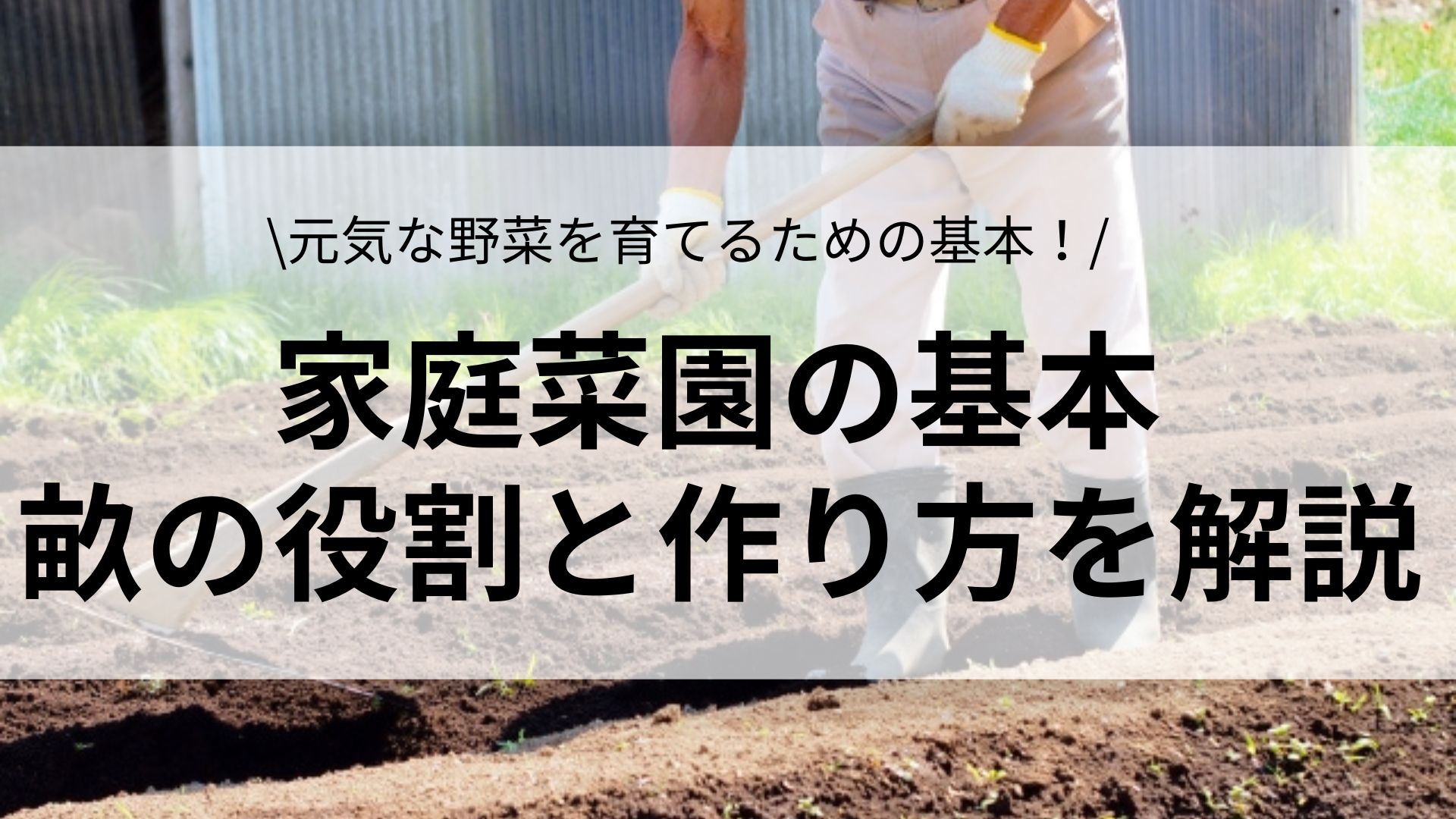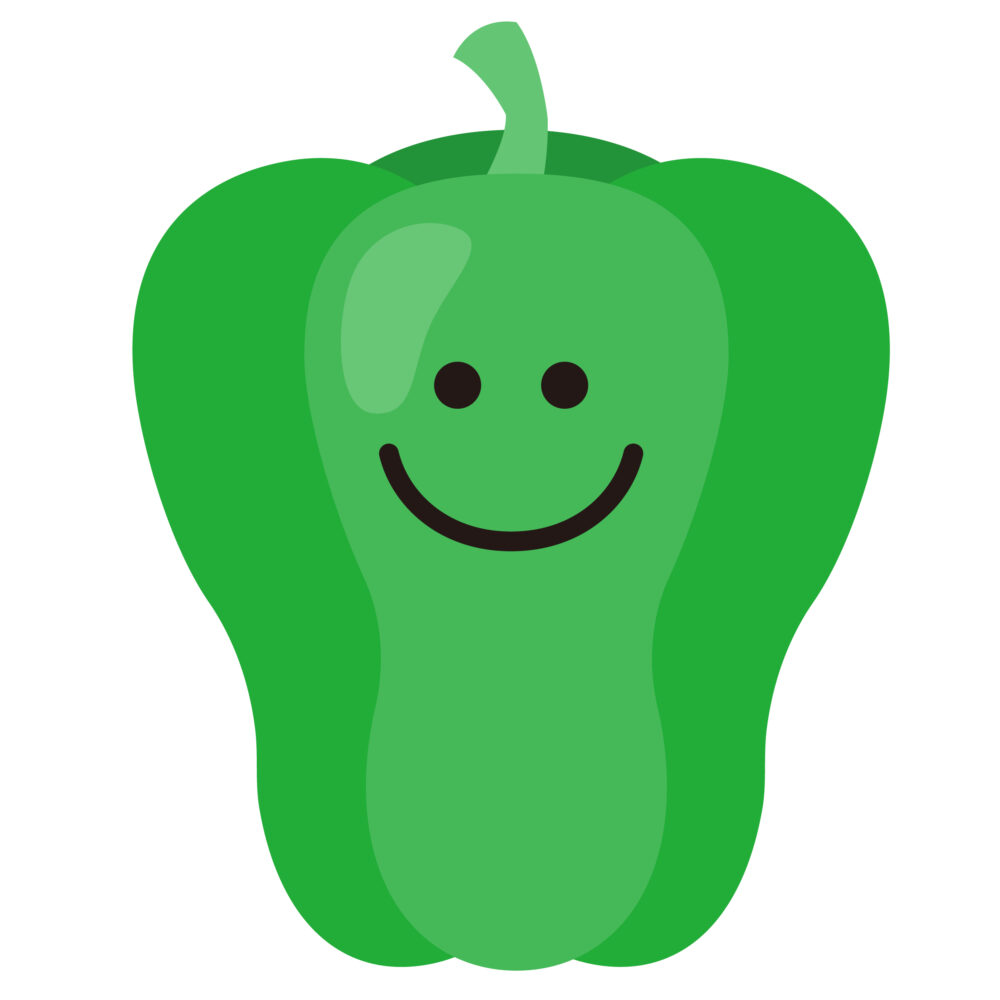 家庭菜園初心者
家庭菜園初心者畑で野菜の苗を植えるまでにやることがたくさんあるなんて知らなかった!



野菜を育てるためには、土づくりをしたり、畝を作ったりとたくさんの工程があります。
今回は、畑によくある細長く土を盛り上げた『畝(うね)』について、役割やつくり方を解説します。
畝とは


畝(うね)とは、畑で野菜などの作物を栽培するために、土を細長く盛り上げたものです。土の水はけをよくしたり、作物の根を張りやすくする目的があり、野菜を育てるためのベッドのような役割があります。
畝立て(畝づくり)とは
野菜を育てるベッドとなる「畝」をつくることをいう。
畝の役割


畝にはさまざまな役割があります。畝の高さによっても役割は変わりますが、ここでは一般的な畝の役割を解説します。
作物の根が張るスペースを十分に確保できる
特に作物が根を張れないほど硬い層が、土の浅い位置にある畑では、畝を立てることで、作土層をとよばれる野菜の根を張るためのスペースを十分に確保することができます。植物は、水分や栄養分を根から吸収するため、根がしっかり張れると植物も健康的によく育ちます。
水はけと通気性が向上する
水はけの悪い粘土質の畑や地下水位が高い畑では雨が降ると水浸しになりがちです。
こうした畑では高めの畝を立てることで、水はけと通気性をよくします。
畝を高くすることで、畝から水が抜けやすくなり、過湿が防げます。 それと同時に土の中に新鮮な空気が入りやすくなり、作物が健康的に育ちます。
土が温まる
畝を立てると地温を高めることができます。土を盛り上げると太陽熱を受けやすいため、畝が温まり、野菜の生長が促されます。
土壌微生物が活性化
畝の上に新鮮な空気、適度な 水分、温度が確保されると土の中の微生物が活動するのに適した環境になります。
微生物が活発になると、有機物が速やかに分解され、作物が吸収できる栄養分が土の中に増えます。すると、作物は養分をスムーズに得られるため、よく育ちます。また、微生物の働きにより、土の団粒化も進みやすくなります。
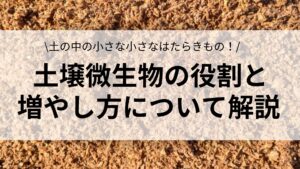
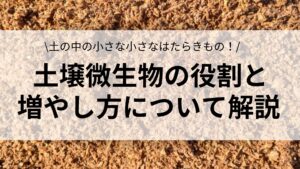
作業性が良くなる
作物を育てるスペースと歩く通路の区別をはっきりすることができるので、野菜の世話がしやすくなります。 また、区画分けができるため、毎年の栽培計画も立てやすくなります。
畝の基本
【畝の基本のポイント】
・畝の幅は60㎝か90㎝が管理しやすい
・畝の高さは、水はけの悪い畑は高めに、乾燥しやすい畑は低めの畝をつくる
・畝は南北方向に向かって立てる
畝の幅
畝の幅は、大きな野菜を育てるなら広い畝が必要になりますが、小さな野菜であれば、畝も狭くて問題ありません。
市民農園や貸し農園を利用する家庭菜園では、幅60cm、もしくは90cmの畝がおすすめです。適度な幅で、ほとんどの野菜が問題なく作れて、管理やすい畝幅です。
幅60㎝の畝
・ハクサイやナスなどの大きな野菜は幅60cmの畝に1列のみ作物を育てます。
・サニーレタスなどの小さな野菜は、60㎝の畝に何列か植えることができます。
幅90㎝の畝
・幅90cmの畝であれば、キュウリやソラマメなどは2列植えることもできます。
・小さな野菜であれば、適度な間隔をあければ何列か植えることができます。
【畝と畝の間は通路として利用する】
・畝と畝の間は通路として、幅は40から50cmとるのがおすすめです。
・狭すぎると歩きづらくなります。
・通路が狭いと日当たりは風通しも悪くなり、作物の生育にも影響を及ぼします。
・通路が広すぎると、限られたスペースを有効活用できなくなる可能性があります。
畝の高さ
畝を高くすると、水はけがよくなります。そのため、水はけの悪い土で野菜を栽培する時は、畝を高めに作ることが基本です。
逆に砂質の土で水はけがよく乾燥しやすい場合は、畝は低めにすることが基本です。
平畝(ひらうね)
・畝の高さが5~10㎝。
・水はけのよい土に適している。
・湿気が好きな野菜(サトイモやショウガなど)の栽培に向いている。
高畝(たかうね)
・畝の高さが10cm以上のもの。平均的な畝の高さは20~30㎝。
・水はけの悪い土に適している。
・乾燥を好む野菜(トマトやスイカやカボチャなど)の栽培に向いている。・水はけの良い土を好むさつまいもなども高畝が適している。
畝の向き
畝は、基本的に南北方向に作って日当たりを確保します。こうすることで、どの野菜にもよく日の光が当たるようになり、作物が生長しやすい環境になります。
東西方向に畝を作ると、草丈が高い野菜の北側の畝が日陰に入ってしまいます。
市民農園や貸し農園を利用している場合は、周りの人がどのような向きで畝を立てているか観察し、同じ方法に畝を立てておけば間違いはないでしょう。
畝の高さは土の水はけや作物の根の張り方によっても異なります。上記の畝の高さは、あくまで一つの目安として自分の畑の土にあった畝の高さを探すことが大切です。
畝立ての方法


【事前の準備】
・土づくりを済ませておく



土づくりとは、野菜が育ちやすい土にするために、苗や種を植える前に、堆肥や肥料を土に混ぜることをいいます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
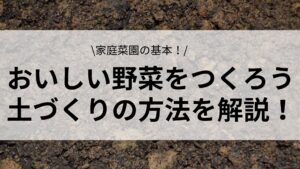
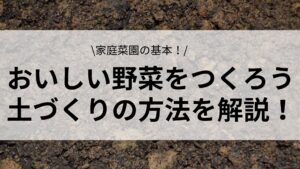
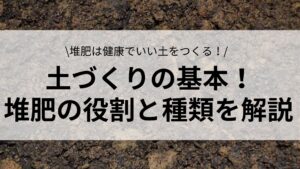
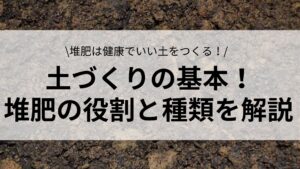
絶対に必要なもの
・クワ
あると便利なもの
- メジャー(畝幅などを図れるものがあれば代用し可)
- ヒモをくくりつけた棒
- レーキ
- プラスチックのパイプ(直径6〜7cm、長さ60〜70cmの塩化ビニール製のパイプが適している。代用として使い捨てでラップの芯も使える。)
畝立ての手順
- 畝をつくるところに印をつける。短い畝であれば、クワの刃の角を使って土に印をかく長い畝を作る場合は棒にヒモをくくりつけたものを用意し、目印として使うとまっすぐな畝が立てられる。
- 目印の内側にクワで土を移動させる。
- この作業を繰り返して作りたい高さまで土を盛り上げる。
- 盛り上げた土の表面をレーキでならす。ない場合はクワの刃の側面を使って土を平らにならす。
- 手元にあれば、さらにプラスチックのパイプを使って畝を平らに綺麗にならす。
- 小石や土の塊りが出てきたら取り除き、隙間ができた畝の表面に土を足しパイプでならす。
- 畝の側面をクワの平面や手を使って押し固める。
- 畝の完成!
畝立てのコツとポイント
畝はまっすぐで表面が平らが理想
まっすぐな畝は見た目がいいことに加えて、その後のマルチングや植え付けも行いやすいです。
土の表面を平らにする理由は、畝にでこぼこがあると、へこんでいる 部分に水がたまり、過度に湿った状態になります。 それにより、生育不良や害虫が発生する原因になります。
また、発芽が揃わず、成長にばらつきが出る原因になります。生長にばらつきがでると、弱い株は枯れてしまったり、病害虫の被害を受けやすくなります。
畝の周囲の角度
シートマルチを利用する場合は、畝の周囲は斜め45度にすると、マルチが張りやすく、剥がれにくくなります。
野菜栽培中の畝の管理
中耕と土寄せと草とり
中耕は畝の表面を軽くほぐす作業です。 土に新鮮な空気が補給され、有用な土壌微生物が活性化するため、肥料効果が現れて野菜の生長が促されます。
畝に草が生えていたら草取りもかねて土をほぐすといいです。
また、野菜の株元に周囲の土を寄せる「土寄せ」も同じ理由で野菜の成長が促されます。
マルチング
畝を裸のままにせず、マルチシートやワラ、枯れ草など有機マルチでカバーしておくと、雨に打たれて土が硬くなるのを防げます。土の湿度と温度が安定し、土壌微生物も活性化するため、野菜の成長が促されます。
ワラや枯れ草などの有機マルチは、土が見え隠れする程度に敷くのがポイント。特に生育初期は土を温めて根を発達させたいので、光が土に届くように薄めに敷くと効果的です。
また梅雨入りして 雨が多い場合には、厚めに敷いておけば、雨が流れて土や養分が流れ出るのを防いだり、泥はねによる病気を防ぐことができます。



マルチングについてはこちらの記事に詳しくまとめました!
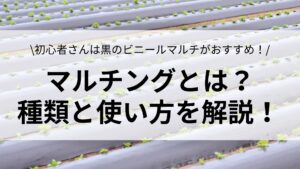
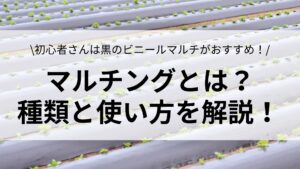
家庭菜園に興味をもった方はシェア畑がおすすめ!



シェア畑は、初心者さんにもちょうどいいサイズの畑をレンタルすることができるサービスです。
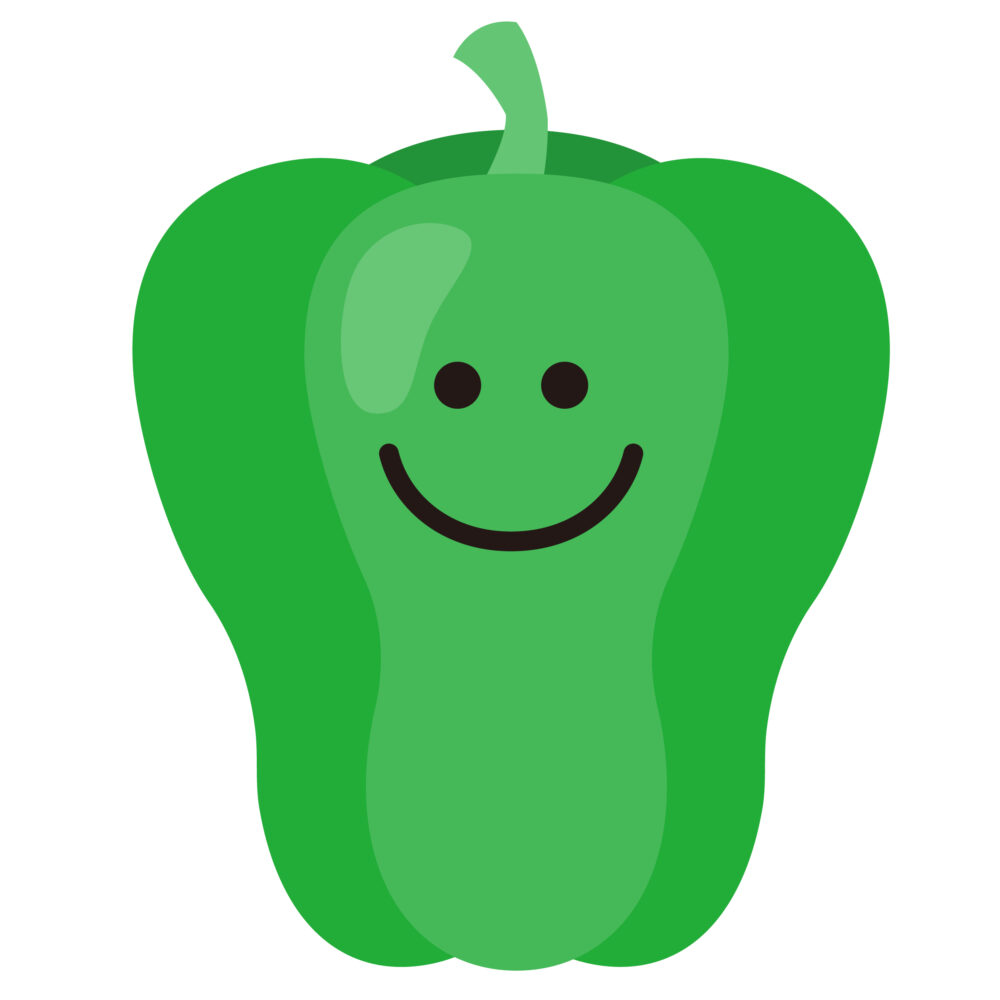
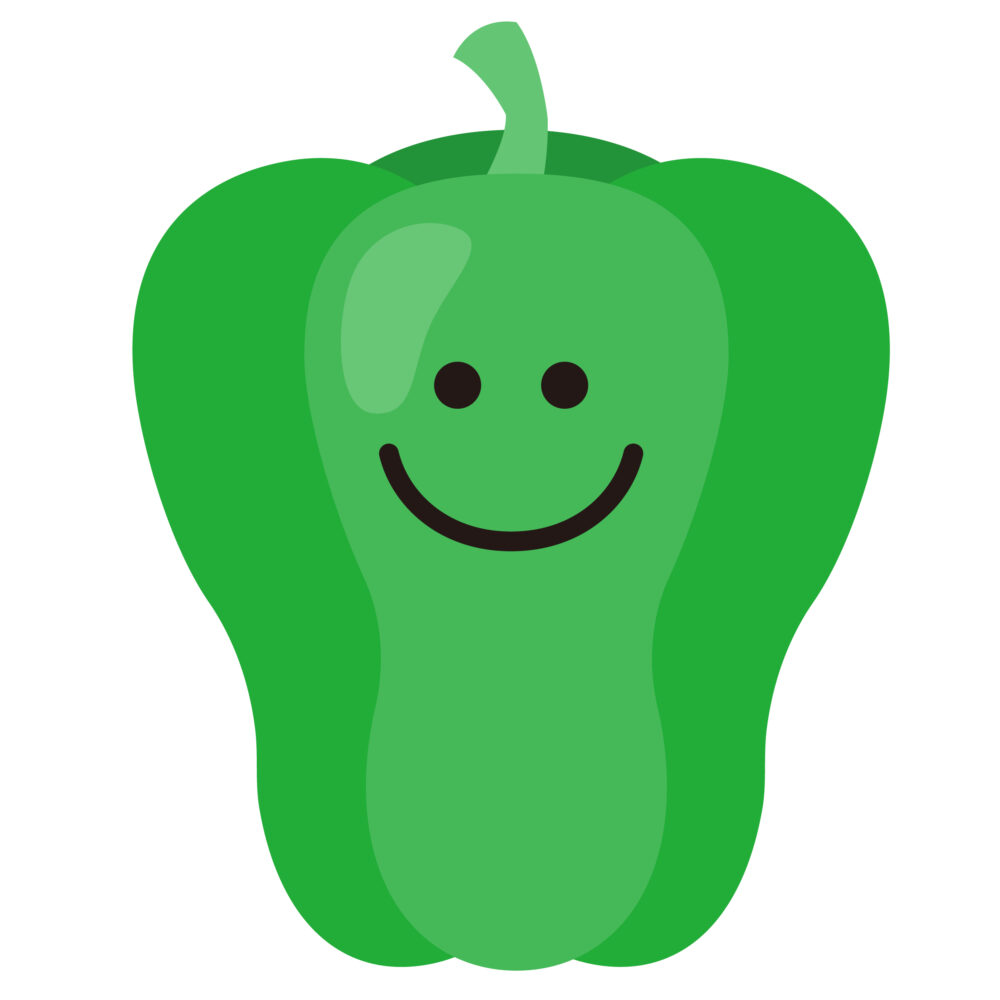
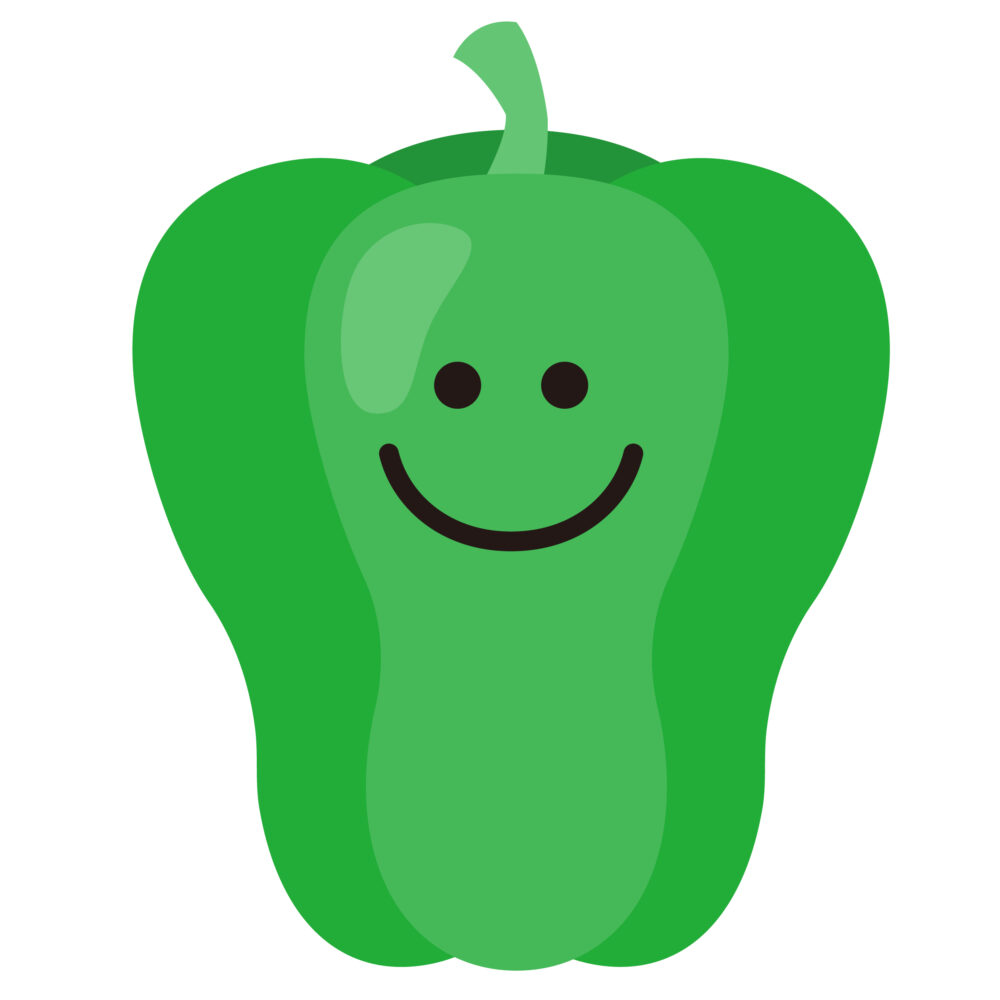
野菜づくりのアドバイザーがいるのも安心できるポイントだね!
シェア畑のメリット
- 水道やトイレなどの設備が充実している。
- 農具(ジョウロやクワなど)のレンタルがある。
- 菜園アドバイザーとよばれる指導員がいることが多いため、初心者でもアドバイスをもらいながら野菜の栽培ができる。
- 野菜づくりの失敗が少ない。
- 堆肥や肥料や苗も利用料金に含まれている。
- 手ぶらで気軽に家庭菜園を始めることができる。
- 定期的に講習会やイベントを開催している。
- オプションで野菜のお世話を依頼できるプランがある。