 畑の水やりの頻度を考える要素
畑の水やりの頻度を考える要素

水やりの頻度は、育てる作物や環境によって変化します。そのため、水やりの頻度を一言で言い表すことは難しいです。水やりの頻度を考える要素を以下にまとめます。
作物の種類(水を欲しがる野菜と乾燥を好む野菜)
作物の種類によって水を欲しがるものと乾燥を好むものがあります。
水を欲しがる野菜:ナス・キュウリ・ピーマン・トウモロコシ・オクラ・サトイモなど
乾燥を好む野菜:スイカ・サツマイモ・タマネギ・ジャガイモなど
水を欲しがる野菜にはたっぷりと水を与える。
乾燥を好む野菜には、水やりを控えめに。
作物の生育状況
人間に赤ちゃんが母乳を頻繁に欲するように、植物も小さい時ほど水やりの頻度が高くなる傾向があります。
例として、ニンジンは発芽するまで土を乾燥させないように水やりをする必要があります。このように野菜の種類によって生育初期は、大人の植物よりも水やりの頻度が高くなるものが多いです。
植物は大きくなると、根を土の奥深くまで伸ばすため、乾いた地表よりも深い層から水分を吸収することができるようになります。
作物が育つ環境
日当たりがよく風通しがいい場所は土が乾燥しやすく水やりの頻度が高くなり、日陰で風通しが悪い場所はジメジメしやすく、土が乾きにくく水やりの頻度は低くなります。
同じ畑の中でも日当たりに応じて水やりの頻度が変わるよ!
季節
季節ごとに気温や日照時間が変化するため、水やりの頻度も変わります。
春と秋:気温の変化が比較的穏やかであるため、土は乾燥しにくく水やりの頻度は低くなる。
夏:気温が高くなり、日照時間も増えるため、土が乾燥しやすく水やりの頻度は高くなる。
冬:気温が低く、日照時間も短いため、土が乾燥しにくい。冬は水が凍りやすいため水やりの頻度は極力低くする必要がある。
天候
適度に雨が降っていれば水やりは不要です。猛暑日が続いたり、まったく雨が降らないときは必要に応じて水やりをする必要があります。
また、晴れが続いているときは土が乾燥するため、水やりの頻度が高くなります。
夏場でも夕立があれば、水やりをしなくていい場合もあります。
土の状態
畑の土は「砂質」「壌土」「粘土質」の3つの土の性質に分けられます。砂の性質によって水持ちや水はけが異なるため、土の乾燥のしやすさにも影響があり、水やりの頻度が変わります。
砂質の土:水はけがよく水持ちが悪いため乾燥しやすい。水やりの頻度は高くなる
壌土:団粒構造(だんりゅうこうぞう)の土。作物が一番育ちやすい土質で水はけ水持ちもいい。水やりの頻度も高すぎず低すぎない。
粘土質の土:水はけが悪く水持ちがいいため、湿った状態になりやすい。水やりの頻度は低めになる
あわせて読みたい
【3つの土の質】畑での野菜づくりに役立つ砂質・壌土・粘土質の土の特徴と対処法を解説
畑での野菜づくりに挑戦したことのある人は、壌土や砂質や粘土質などといった土の質を気にしたことはありませんか?おいしい野菜を育てるためには、土について知ること…
あわせて読みたい
【野菜の種類別の土づくり】野菜と土の質にあわせた土づくりのコツを解説!〜砂質・壌土・粘土質〜
畑の土や庭の土は、地域や環境によって異なります。土の質は、大きく分けて3つの性質に分類されます。 ①サラサラとした「砂質の土」 ②ずっしりと重みのある「粘土質の土…
ほとんどの野菜がよく育つ『団粒構造の土』は水持ちも水はけもいいよ!
団粒構造について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい
団粒構造とは?フカフカで良い土を作るための方法や調べ方を解説!
作物が健康に育つためには、根から水分や栄養分を吸収していく必要があり、根が埋まっている土の環境は重要な要素になります。野菜づくりには、フカフカな土が良いとい…
水やりをする目安
土の表面が乾いたとき
土の表面が乾いていたら、土を2~3㎝軽く掘ってみます。表面が乾いてても土の中が適度に湿っていれば水やりは不要です。
2~3㎝掘った土もカラカラに乾いていたら水やりをする目安にします。
土が乾きやすい状況としては、気温が高い、風が強い、日当たりがよい、雨が降っていないなどがあげられます。
葉がしおれたとき
葉がしおれてくるのは、植物が水分不足になっているサインです。
葉がしおれる前に水やりをすることが大切です。
水やりをするタイミングの基本
朝晩の涼しい時間帯
水やりの時間帯は、朝晩の涼しい時間帯が最適です。
日中に水やりをすると、水が蒸発してしまい、植物が水を吸収しにくくなります。
暑すぎる、寒すぎる環境での水やりは、植物の根を傷める原因となり、植物の発育が悪くなるなどの影響があります。
季節ごとの水やりのタイミング
水やりは季節ごとに適したタイミングがあります。
特に、真夏と真冬は注意が必要です。同じ場所に植物を植えていても、季節が変わると植物にとっては全く違う環境になります。
- 夏:早朝または気温が下がった夕方以降
- 冬:午前中からお昼の気温が上がる時間帯
夏の水やりは早朝または気温が下がった夕方以降に行う
特に夏場の気温が30度を超える日は、お昼から午後の水やりは避けましょう。
植物に与えた水が温まり、お湯になるため、植物の根が傷んでしまいます。
冬の水やりは午前中からお昼の気温が上がる時間帯に行う
冬の夕方は気温が下がるため、この時間帯に水やりをすると残った水分が凍ってしまう可能性があります。
根やその周囲が凍ると根のダメージにつながり、植物の元気がなくなってしまいます。
水やりのコツ
根元にゆっくりと水をかける
勢いよく水をかけると、土が流れてしまったり、根が傷ついたりすることがあるので、ジョウロやホースを使って、根元にゆっくりと水を与えるようにします。
葉に水がかかると、葉焼けを起こしたり、葉がジメジメして病害虫が発生しやすくなります。
マルチングをする
雨や水やりの時に、土や水が植物の葉や茎に飛んでしまうと、植物が病気になってしまう可能があります。
あらかじめビニールマルチをしておくか、植え付けてしまったあとであれば、ワラを使ってマルチングをするのもおすすめです。
あわせて読みたい
【家庭菜園】初心者さんは迷ったら黒のビニールマルチを使おう!マルチングの種類と特徴を解説!
家庭菜園で使うマルチングってどんなものなの? 作物を育てる土をビニールやワラなどで覆うことをマルチングといい、雑草の予防や土の保護を目的に使われるよ! マルチ…
水やりの量は多すぎず少なすぎず
一度にあふれるほどに大量の水をあげてしまうと、植物の根は水に溺れて酸欠となり「根腐れ」を引き起こす可能性があります。
あわせて読みたい
野菜の根腐れは復活する?根腐れの原因と手遅れになる前にできる予防・対処について解説
家庭菜園で野菜を育てているときに、水やりも肥料も十分に行っているのになぜか枯れてしまう。植物の根元から元気がなくなって腐ってしまった。こんな植物の症状に悩ん…
また、過剰な水やりは、土の中の栄養分を水とともに流してしまうことにもつながります。
水を与える量が少なすぎると、表面は湿ったように見えても、土の中までまったく水が浸透していなかったというケースもあります。
水が少なすぎると植物が吸収する前に蒸発してしまうため、土の中が程よく湿る程度の水をあげましょう。
水やりのNG行動

- 花に直接水をあてる
- 葉に直接水をあてる
- 水を与え過ぎる
- 気温の高い時間帯の水やり
- 冬の夕方以降の水やり
花に直接水をあてる
花に水が当たると花粉が流れ出てしまい、実の付が悪くなる原因になります。ナスやトマトなど、花を咲かせたあとに実る野菜は特に注意が必要です。
葉に直接水をあてる
葉に水を直接かけると、水滴がレンズのように太陽光を集めて一部の葉が焼けてしまう「葉焼け」の原因になる場合があります。
水を与え過ぎる
植物は水を求めて土の奥深くに根をどんどん伸ばしていく性質があります。水を与え過ぎてしまうと、根が生長をさぼってしまい、吸収できる栄養分も少なくなり、株自体の元気もなくなってしまいます。
気温の高い時間帯の水やり
気温が30度を超える時間帯の水やりは、水が温まって根を傷める原因になります。特にお昼から午後の気温が高い時間の水やりは避けましょう。
冬の夕方以降の水やり
気温が下がるため、残った水分が凍ってしまう可能性があります。水が凍ると、植物の根を傷める原因になるため、冬場は気温が上がる午前中や昼頃に水やりをしましょう。
畑の水やりの考え方
畑での野菜づくりは、屋根がなく、自然にさらされているため、露地栽培(ろちさいばい)とよぶこともあります。
露地栽培の特徴は、雨が降ったり、夜露が降りたりと、自然の力で水やりがされる機会があることをいいます。
そのため、露地栽培では、必要以上に水やりをする必要はなく、自然の力での水やりを基本とします。
毎日の朝晩の水やりは、水分の与え過ぎになってしまう場合もあるため、しばらく雨が降らない時は、土の状態をよく観察し、必要に応じて水やりを行いましょう。
水やりのために畑に通えない場合

特に2023年の夏場のように、猛暑日が30日以上続き、雨も降らない天気の場合は、ほぼ毎日水やりが必要になります。
実際に私も、2023年の夏場は、ほぼ毎日水やりをしていました。
夕方のまだ暑さが残る中、重たいジョウロをもって何往復も井戸と畑を行ったり来たりするのは、正直楽ではありませんでした。
私は、職場と借りていた市民農園の距離が近かったので、仕事後に畑に寄ることができましたが、毎日畑に通うことが現実的でない方も多いと思います。
そんな方は、民間企業が運営する「シェア畑」がおすすめです!
市区町村が運営する市民農園に比べて、シェア畑は利用料金が高くなりますが、水やりなどのお手入れもオプションでつけることができます。
誰かの力を借りながら野菜を育てるのも一つの手段として考えておいてもいいかもしれません。
シェア畑についてはこちらの記事に詳しくまとめました!
あわせて読みたい
【貸し農園の比較】市民農園とシェア畑の料金の相場とメリットデメリットを解説!
畑を借りて家庭菜園にチャレンジしようとすると、こんな疑問を持った方はいませんか? 市民農園とシェア畑の違いは? 料金の違いや相場は? それぞれの農園の向き不向き…
補足
水やりそのものは簡単な行為であっても、水やりをするにあたって考慮しなくてはならない点がたくさんあります。
水やりは奥が深く、作物や育てる環境によって異なるため、「こうすればいい」という正解を出すのは正直難しいです。
この記事の内容を参考に、自分の畑や作物の様子を見ながら水やりの量や頻度、タイミングを研究してみてください。
家庭菜園に興味を持った方は『シェア畑』がおすすめです!
家庭菜園にちょうどいいサイズの畑が借りられます!
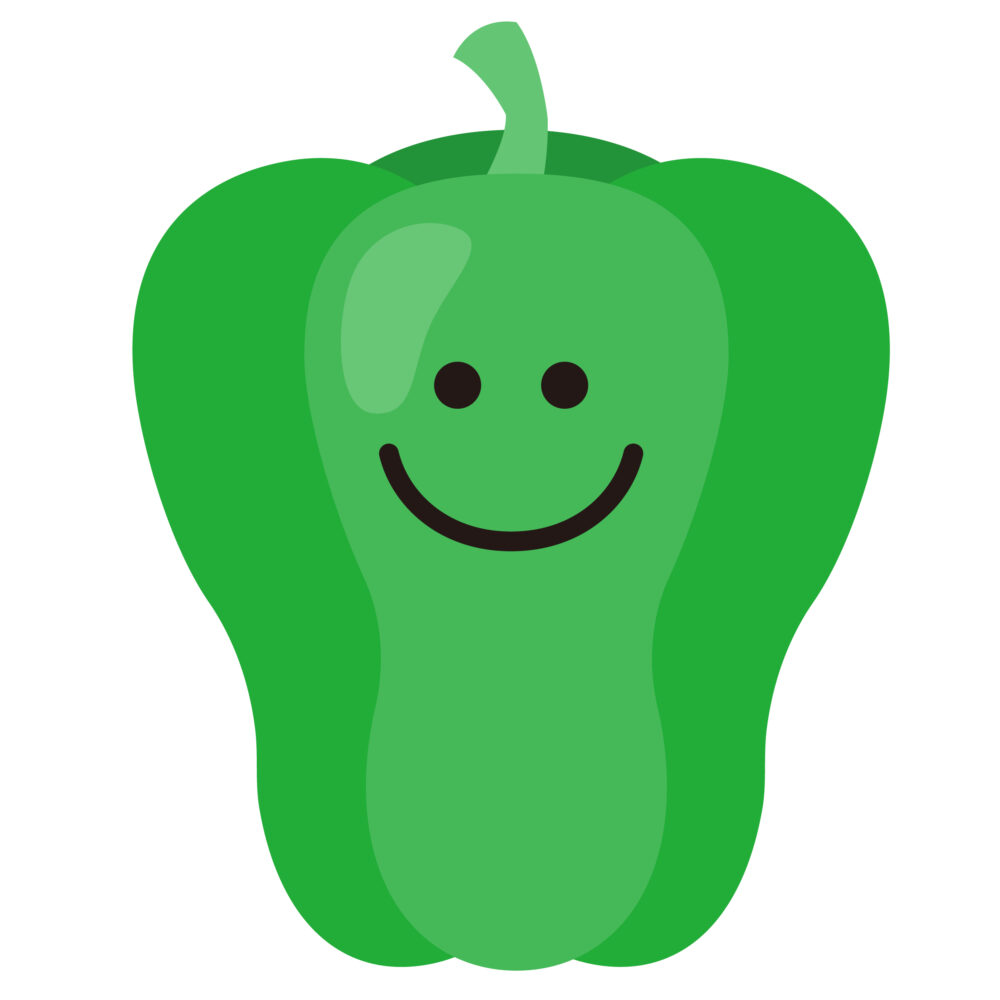 家庭菜園初心者
家庭菜園初心者







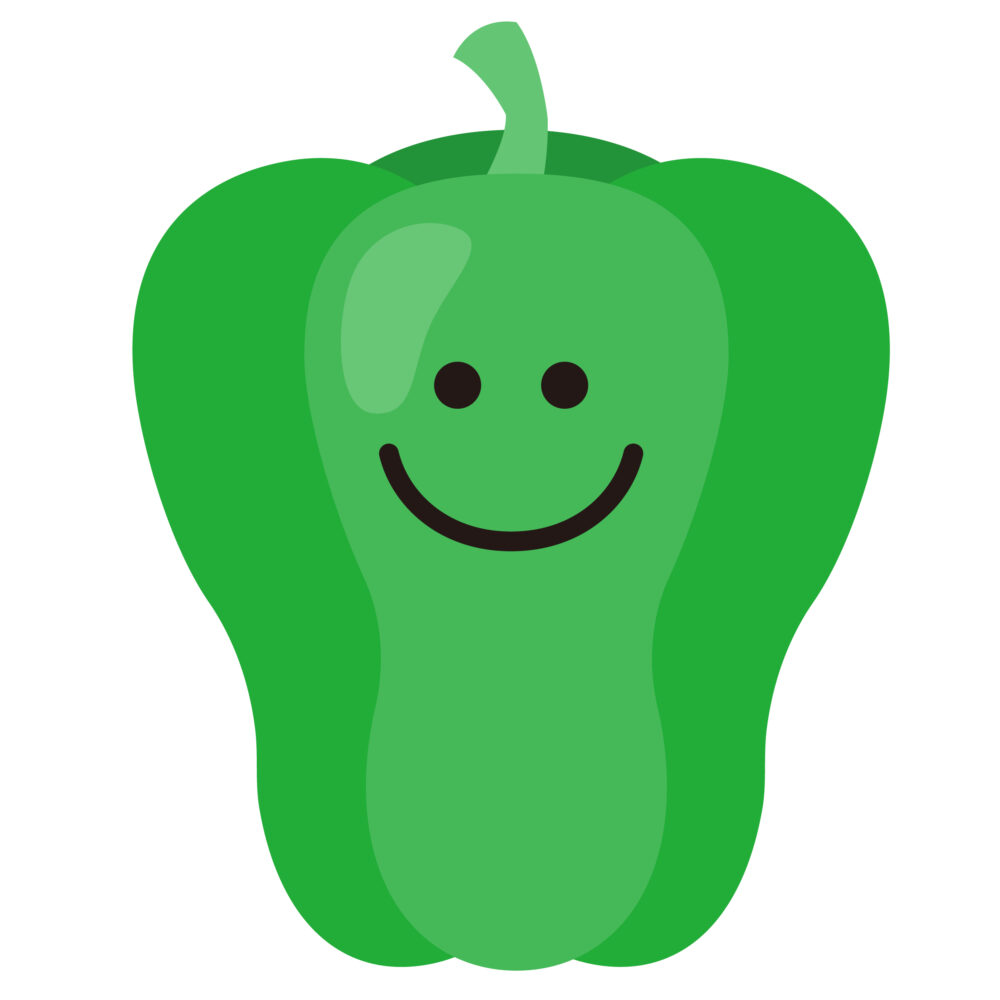
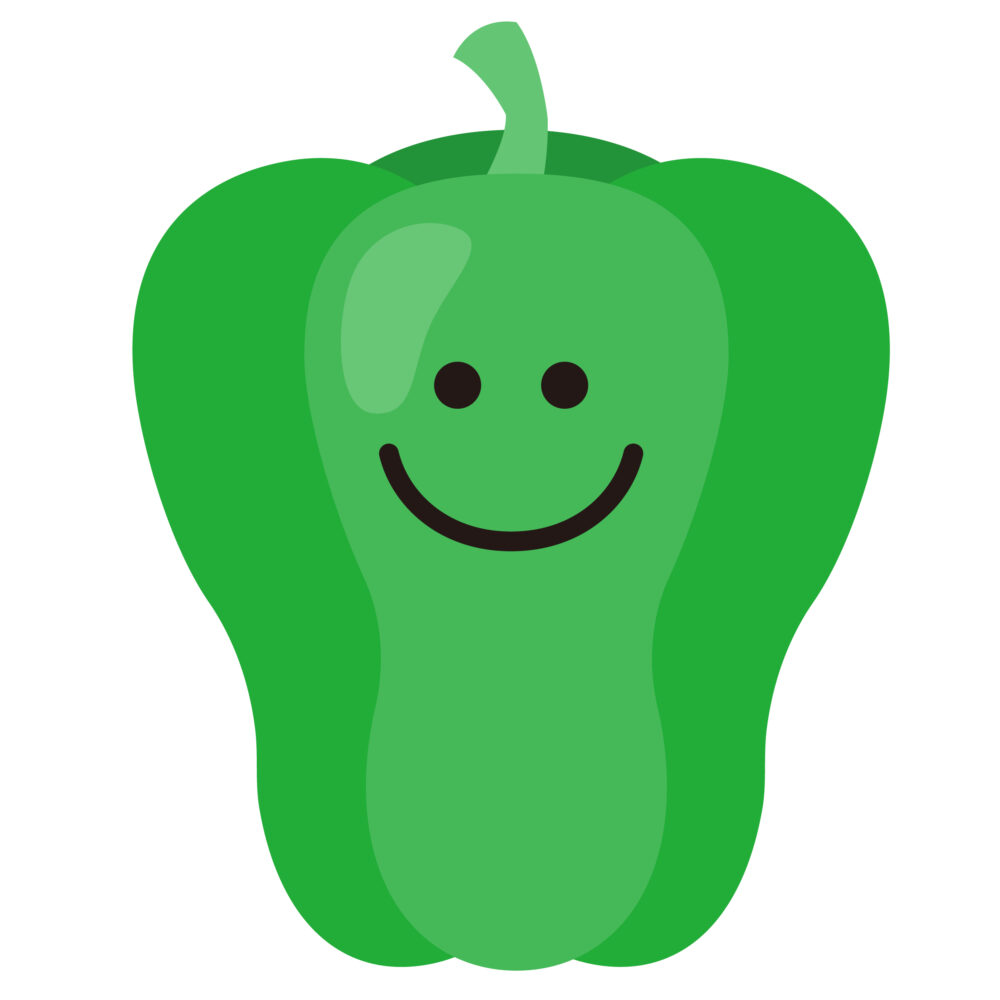
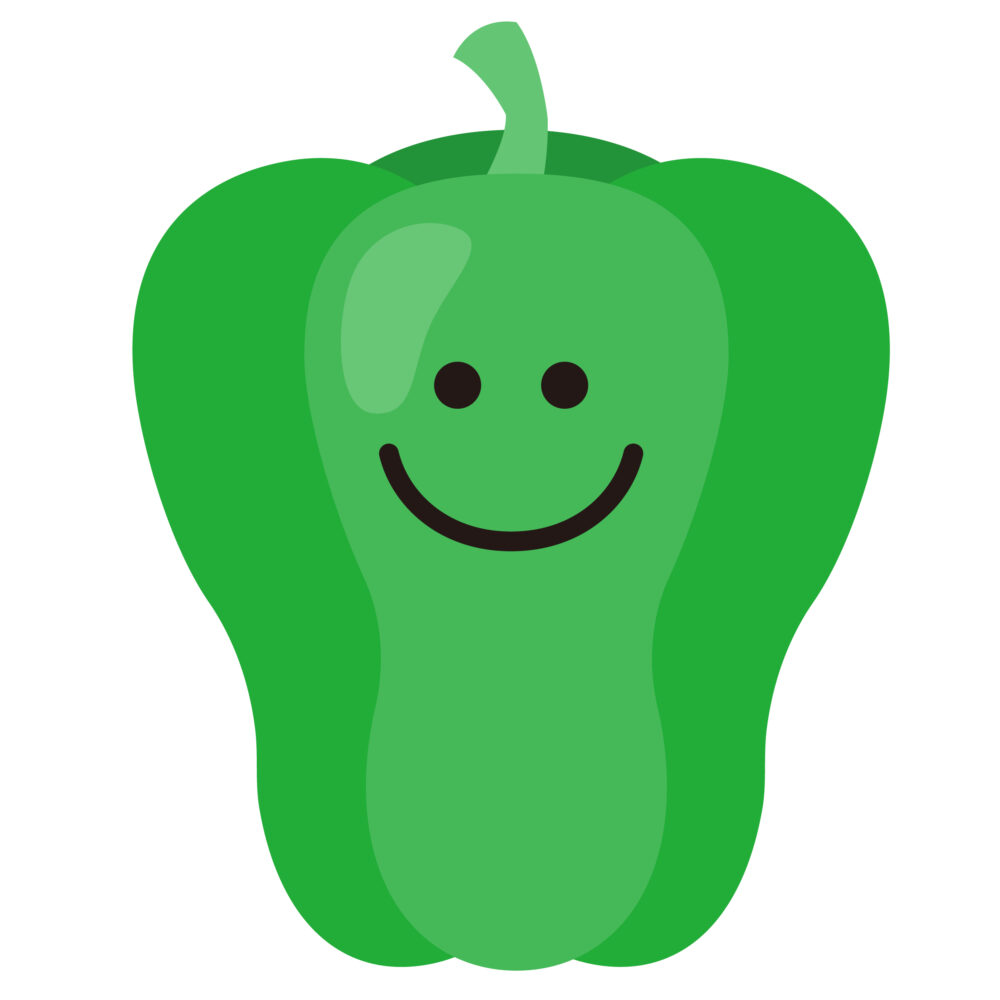






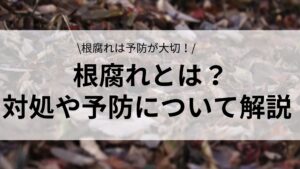
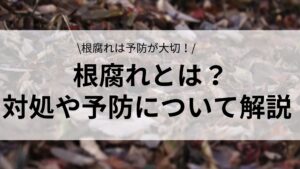



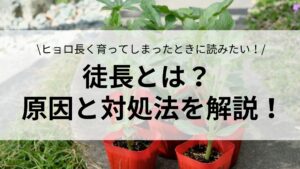
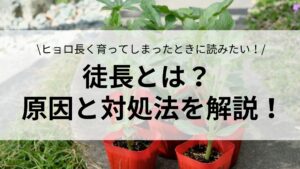
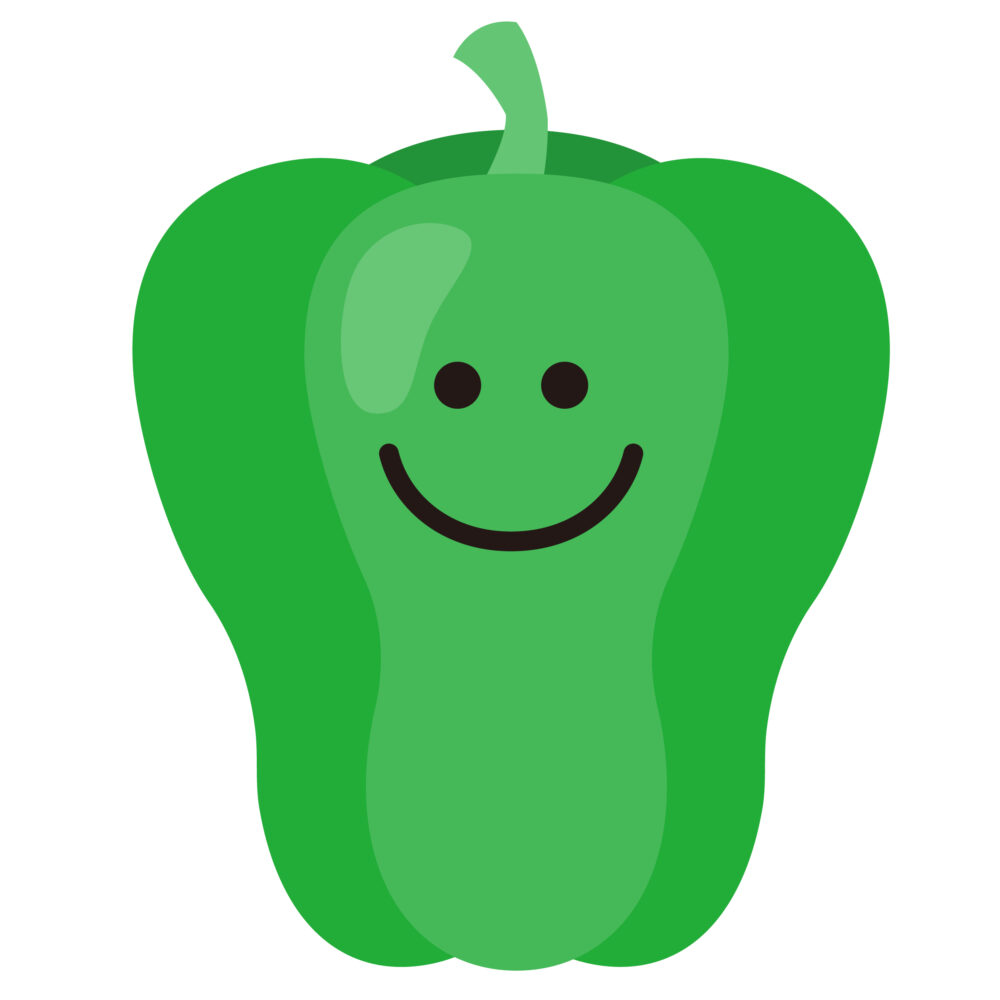
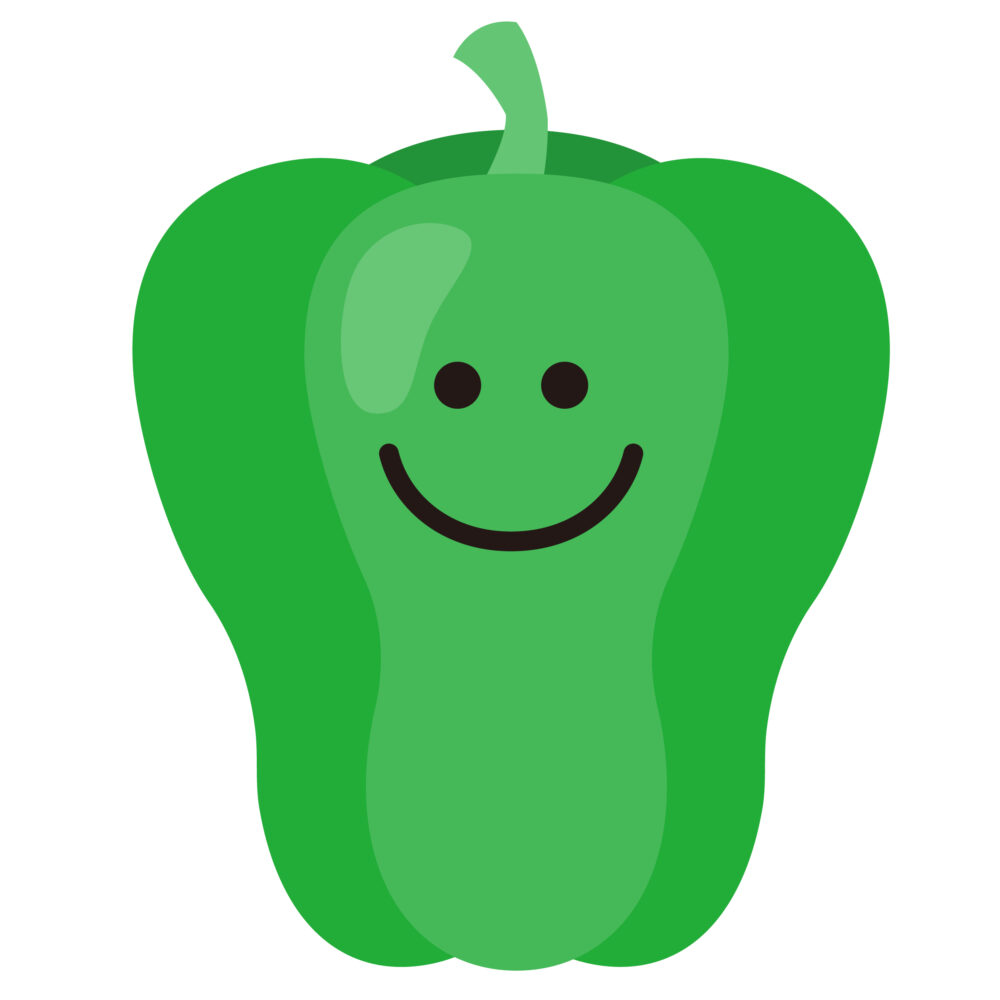
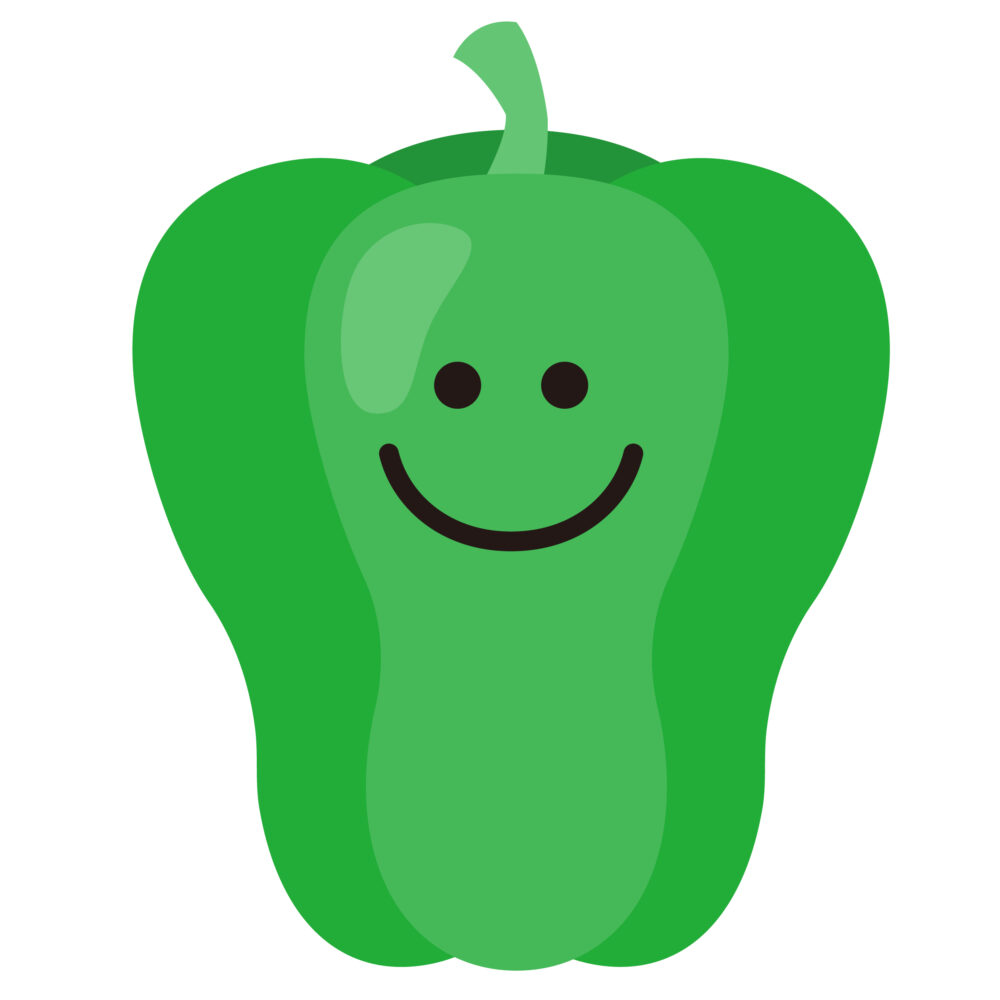









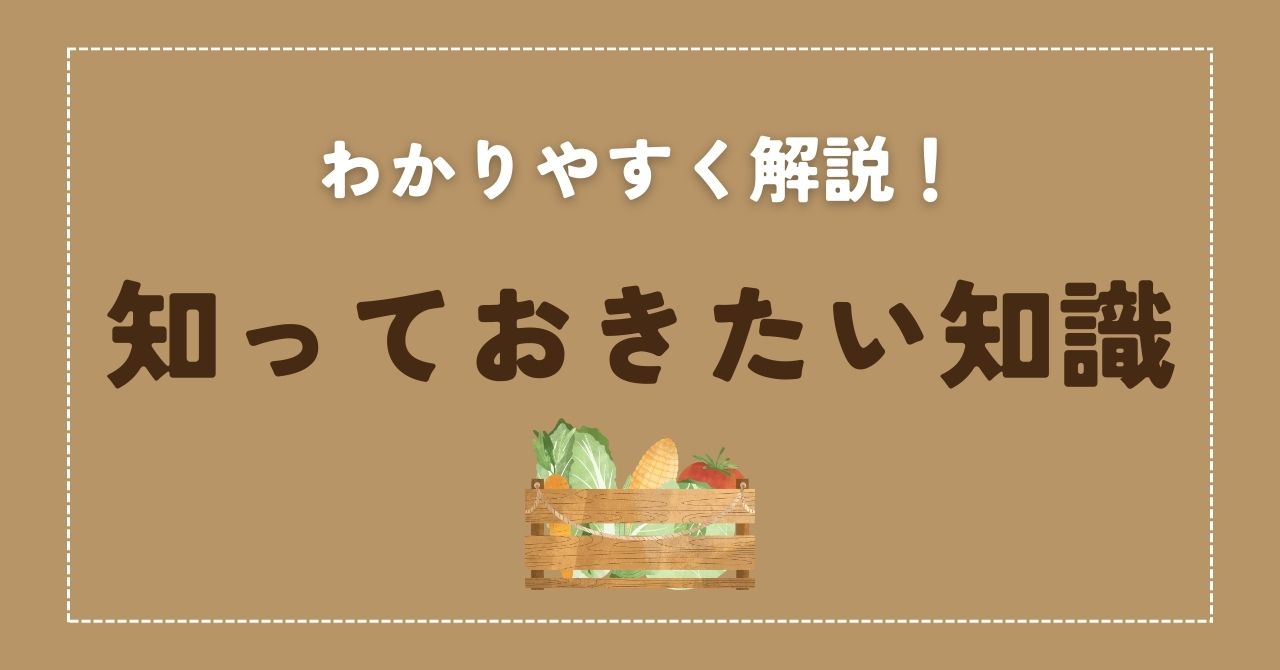

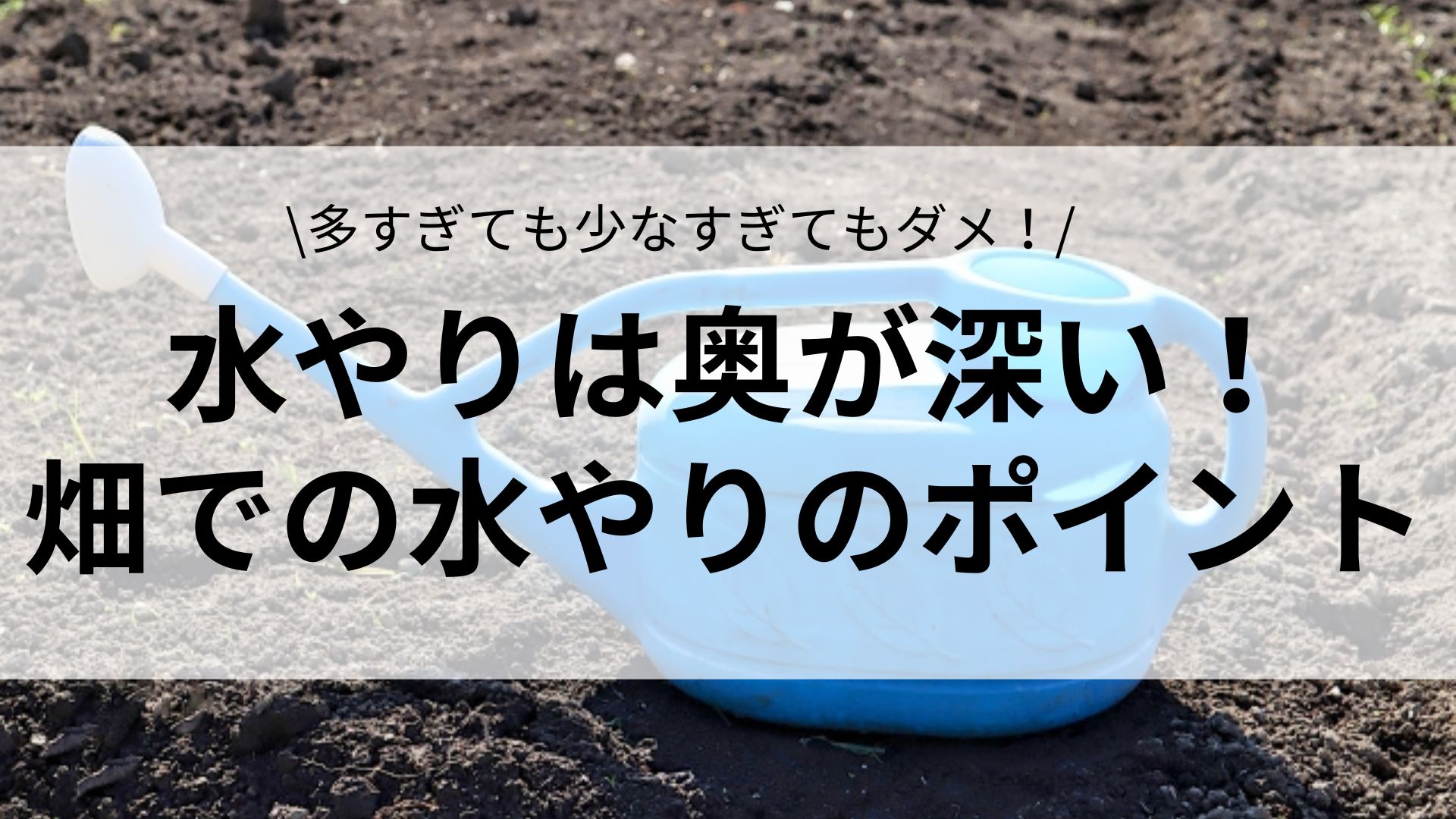


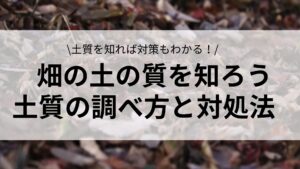
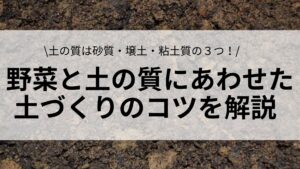
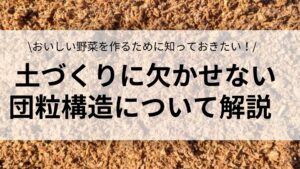
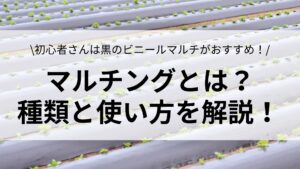


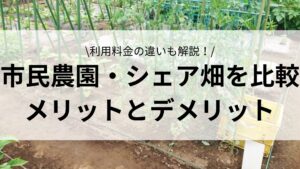
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 家庭菜園での水やりは、土壌の種類によって適切な頻度が異なります。砂質土壌は水はけが良く乾燥しやすいため、頻繁に水やりが必要です。一方、粘土質土壌は水持ちが良いため、水やりの頻度は低くて済みます。壌土は水はけと水持ちのバランスが良く、最も理想的な土壌です (おいもの市民農園ブログ)。 […]