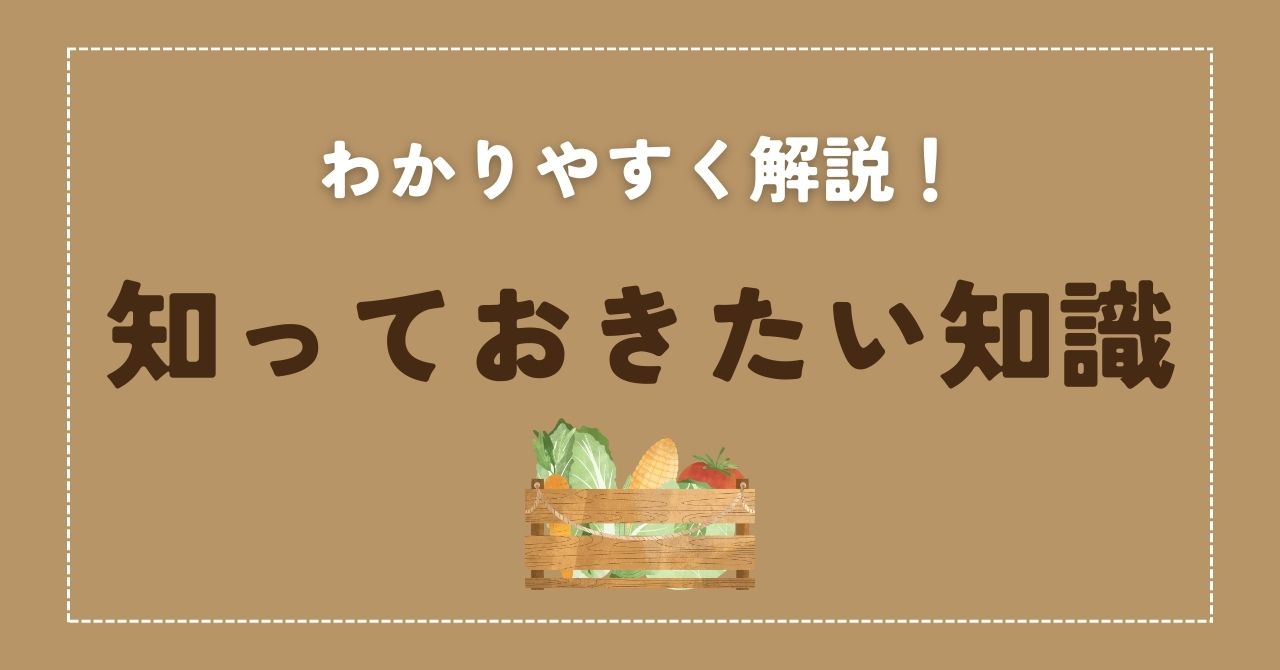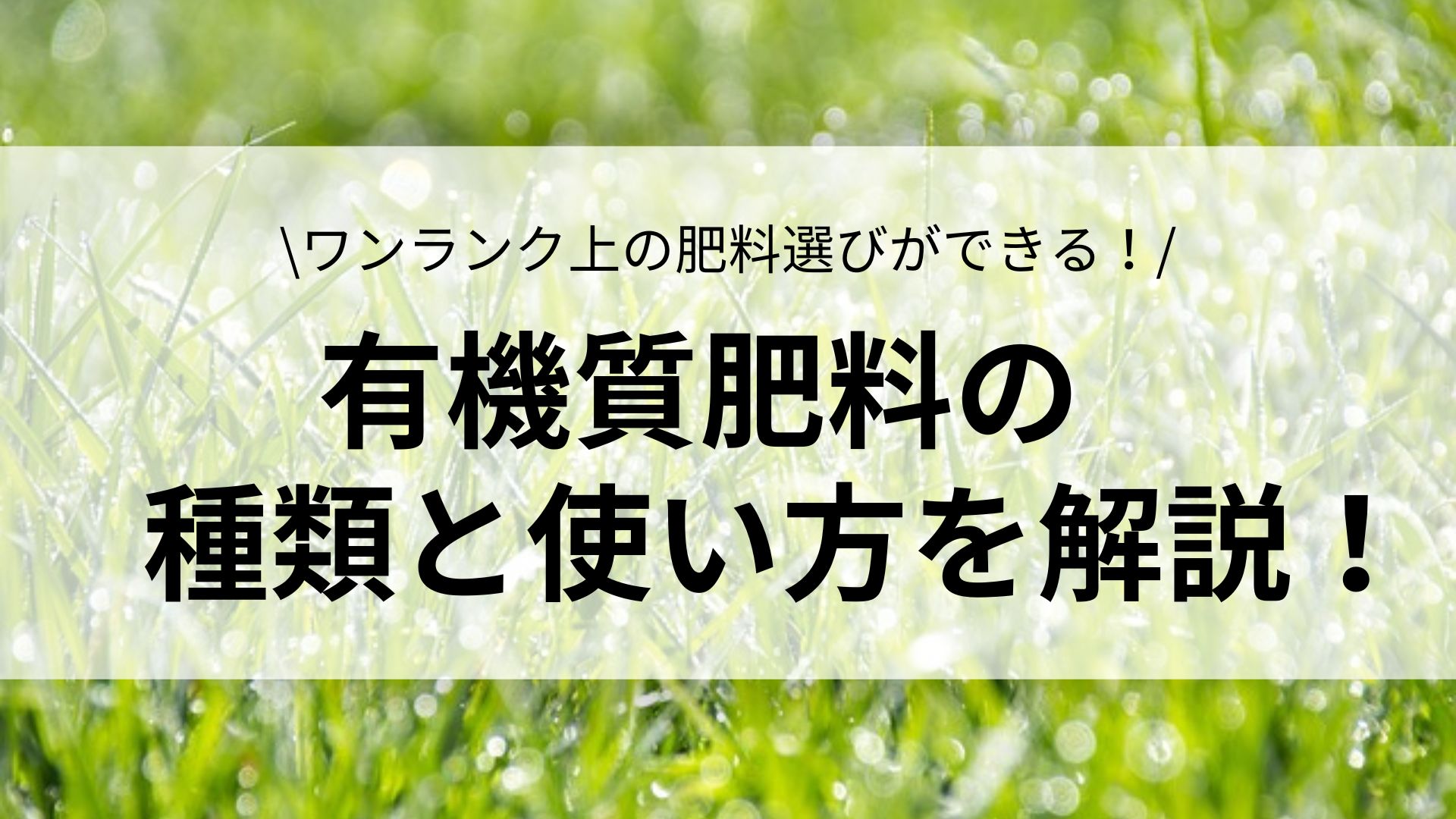家庭菜園をする方は、有機栽培にチャレンジしてみようと思ったことがある方は多いのではないでしょうか。今回は、有機栽培で使用できる、有機質肥料の種類と特徴について解説します。この記事を読むことで、元肥や追肥に向く有機質肥料が分かり、肥料選びがワンランクアップします!
この記事の結論
・元肥には、油かすと米ぬかなどの生のものが向く。
・追肥には、発酵油かすなどの発酵系が向いている。
・肥料は土に残ることが多いので年々施肥量を減らし、肥料を与えすぎないことが大切。
野菜の生長と栄養分の関係

植物は、太陽のエネルギーを利用して二酸化炭素と水からでんぷんを作り出す光合成を行い、そのでんぷんを利用してたんぱく質や脂質を合成し、自分の体を作って生長していきます。植物が健全に成長するには14の要素(ミネラル)が必要と言われ、これらの多くは主に根から吸収されます。
植物が最も多くの量を必要とする 養分が、チッソ・リン酸・カリウムの3要素です。
ついで中量要素、微量要素と続きます。
14の要素は自然界では不足することはありませんが、畑で野菜を作る場合にはどうしても不足してしまいます。そこで必要に応じて堆肥や有機質肥料を施して養分を補います。この時に用いられるのが「肥料」です。
野菜の生長に欠かせない14の要素

野菜の生長に欠かせない要素として、「三要素」と呼ばれる、チッソ・リン酸・カリウム以外にも、カルシウムなどを含む「中量要素」、鉄や亜鉛などを含む「微量要素」に分けれらます。
植物の生長に必要な「三要素」
チッ素(N)
- 葉や茎の生長を促す重要な要素。
- あらゆる植物の生長に必要な養分で葉を茂らせ茎を太くする。
- 特に葉菜類はチッソ主体の肥料でよく育つ。
- チッソが不足すると黄色くひょろひょろになる。
リン酸(P)
- 細胞壁を丈夫にする。
- 根の成長や花や実をつける時に欠かせない 要素。
- リン酸が不足すると実つきが悪くなる。
- 果菜類や根菜類に与えると良い。
- 生体内エネルギーの要でもある。
- 不足すると発育が悪くなり、開花や結実に影響する。
カリウム(K)
- 細胞液に溶け込んでイオンの濃度を一定に保つ役割がある。
- 根や実の成長を助ける大切な要素。
- 不足すると発育が悪くなり病気の抵抗性が落ちる。
- 果菜類や根菜類の栽培に不足すると味が悪くなることがある。。
中量要素
カルシウム(Ca)
- 3要素に続いて重要な栄養。
- 細胞膜を丈夫にする 役割。
- 不足すると細胞壁が弱くなりトマトの尻腐れ病などが出やすくなる。
- 根の先端の成長にも欠かせない。
マグネシウム(Mg)
- 葉緑素を構成する主要な要素。
- 不足すると光合成の量が減る。
- 不足すると葉が黄色く変色する。
- 野菜がリン酸を吸収するのを助ける働きもある。
硫黄(S)
- タンパク質を構成する要素。
- 不足すると古い葉が黄色くなる。
- 欠乏すると枯れてしまう。
微量要素
- これらの微量要素も植物の健全な成長に必要。
- 光合成、アミノ酸合成、酵素の活性化に関わるなど、様々な役割を持っている。
- 微量要素は畑の土の中に元々含まれている量で十分なので補給する必要はない。
- ただし土がアルカリ化すると根から吸収できない状態になるものもあり、欠乏症状が出ることがある。
- 塩素(Cl)
- ホウ酸(B)
- 鉄(Fe)
- マンガン(Mn)
- 亜鉛(Zn)
- 銅(Cu)
- モリブデン(Mo)
- ニッケル(Ni)
有機質肥料
- 米ぬかや油かすなどの有機物でつくられた肥料のこと。
- 堆肥だけでは不足する養分を補う目的がある。
- 効き出しが遅いので堆肥と共に早めに施しておくことがポイント。
【元肥向き】ゆっくり効く有機質肥料
・施してから2〜3週間後に植え付ける。
・肥料効果が穏やかにじわじわ出る。
油かす
- ナタネ油やコーン油など搾りカスのこと。
- チッソが豊富に含まれているのが特徴。
- ゆっくり効く生の有機物なので元肥として利用。
- あらゆる野菜に使える。
- ぼかし肥料作りの材料にもなる。
米ぬか
- 精米のときに出るカス。
- 最も安価で手に入りやすい。
- リン酸がやや高く油かすとブレンドして元肥に使うといい。
- マグネシウムや鉄分なども含んでいる。
- コイン精米所、米穀店などで手に入る。
- ぼかし肥料の材料や堆肥作りにも利用する。
【追肥向き】 速く効く有機質肥料
・発酵済みなので肥料効果が速やかに出る。
・すき込んですぐに植え付けられる。
発酵油かす
- 油かすを発酵させたチッソ主体の肥料であらゆる植物に利用できる。
- 油かす以外の有機物をブレンドして養分バランスを良くしたものが多い。
【使い方】元肥に使うほか、肥料効果が速やかに出るので追肥にも利用できる
発酵鶏ふん
- 鶏ふんを発酵させたもの。
- リン酸が豊富で果菜類に利用すると実つきがよくなる。
- 乾燥鶏ふんも利用されるが独特の匂いがある。
- 家庭菜園では匂いが穏やかな発酵鶏ふんがおすすめ。
【使い方】・元肥や追肥に使用できる。・ 化学肥料並みの即効性があるので使用量に注意する。
ぼかし肥料
- 油かす、魚かす、米ぬかなどの数種類の有機物をブレンドして発酵させた 肥料。
- 肥料堆肥だけでは不足する養分を補うのに使う。
- 三要素のバランスがよく、中量要素、微量要素も含まれている。
【使い方】・元肥にも追肥にも使用できる。・あらゆる野菜に利用できる。
土の酸性調整に使うもの
有機石灰
- カキ殻石灰や貝化石が含まれる。
- カキ殻石灰は牡蠣の殻を粉末にした天然の石灰資材。
- カルシウムの補給や土壌の酸度を中和させるために使用する。
- 穏やかに効き目が続く。
【使い方】
植付の2〜3週間前に堆肥や有機質肥料と一緒に混ぜておく。
草木灰
- 草や木を燃やして作られた灰。
- カリウムを多く含む。
- 土壌の酸度調整に利用されることもある。
- ケイ酸の補給にも役立つ
【使い方】チッソをほとんど含まないので油かすなどと一緒に使う。
元肥には生タイプ・追肥には発酵肥料
元肥として使いやすいのは油かすです。 養分バランスが良くてあらゆる野菜に向いています。 米ぬかもよく利用されますが、三要素のうちチッソが少なくリン酸が多めです。
使うならチッソが豊富な油かすと合わせて使うといいでしょう。
追肥に向くのは肥料効果が速やかに出る発酵タイプの有機質肥料です。
発酵タイプの有機質肥料は、元肥にも利用できます。
ただし、生のタイプの油かすや米ぬかより少々割高であるデメリットがあります。
土壌の生物活性が高まれば、有機質が速やかに分解されて野菜の栄養分になるため、油かすや米ぬかも追肥に使えます。
肥料の量は年々減らしていく
野菜作りで避けたいのが必要以上の堆肥や肥料を施すことです。足りなくても問題ですが、入れすぎた堆肥や肥料はすぐに抜くことができません。
土の中の微生物が持つ消化能力を超えて、畑に養分を与えると野菜に病気や害虫の被害が多くなることもあります。
野菜作りを始めて間もない人ほど肥料を多く入れる傾向があるので注意が必要です。
・肥料は施しすぎてしまうとすぐに抜くことができない・肥料過多は病害虫の被害などを引き起こしやすくやる・肥料は与えすぎないことが大切
有機栽培の場合、施した堆肥や有機質肥料は1年ごとに全部消費されず、少なからず畑に残り、次作に栄養分が持ち越されます。
ただし、有機物の分解スピードが早い 砂質の畑では有機質の分解が早いため、それほど問題になりません。
粘土質の畑や寒い土地の畑、まだ土ができていない新規の畑では思いのほか養分が残っていることが多いです。
毎年同じ量の堆肥や有機質肥料を施しているとたちまち養分過多の畑になってしまいます。
そのため、養分がたまることを考え、年々施肥量を控えめにしていくということです。
畑によって堆肥や肥料を消化できる能力は違いますが、適量は育てている野菜が教えてくれます。
野菜の病気や害虫の被害などのトラブルが増えてきたと感じたら、堆肥や肥料の量は適切なのか見直す必要があります。堆肥や有機質肥料は畑の土の中にたまるということを覚えておきましょう。
・畑の土質や環境によって肥料を消化できる量が変わる。・砂質の土は肥料や堆肥の消化が早い。・粘土質の土はもともと肥えた土なので養分過多になる可能性がある。・養分過多や肥料切れを起こしたは、野菜に症状がでるためよく観察する。